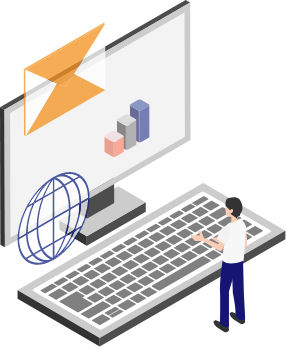2020年は、感染症が拡大し、緊急事態宣言がなかなか解除されないという、今まで経験したことのない状況に直面しました。
今回は、どのようにしてその問題に立ち向かっていくのかについて解説します。
その対策の一つが生活する中で一人ひとりが取り組む「#social distance(社会的距離を保とう)」です。
目次
感染症対策で新たにテレワークを導入した企業の状況
新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークを導入する企業が増えてきました。テレワーク相談センターに寄せられる相談件数は、通常の約2.5倍にも膨らんでいます。
東京商工会議所の東商会員企業を対象とした調査によると、実際に都内の企業でテレワーク導入済みの企業は26.0%、導入検討中の企業が19.5%となっています。この調査では従業員規模が大きい企業ほど、導入率が高まる結果となりました。テレワークを導入するには、外部から社内システムを安全に利用できるICTの環境構築が必要となり、それなりの費用がかかるため、小規模企業にとって負担が大きくなります。とはいえ、東京都の補助金「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金」では、パソコン10万円未満と制限があるものの、社外からの情報機器を購入するための費用を全額補助しています。こうした補助金を活用することで導入は中小企業にも広がっています。
Merchant Savvy発表「Global Remote Working Data & Statistics Updated Q1 2020」の世界各国のテレワーク状況の中で、「柔軟な仕事場のポリシーを採用する企業(テレワークを認める企業)」と「柔軟な仕事スタイルがニューノーマルになると考える人々(テレワークが望ましいと考える人)」の比率を示しています。その中で、アメリカは69%、イギリスは68%、ドイツにいたっては80%の企業がテレワークを採用しており、日本は32%の数値でしかありません。一方、「テレワークが望ましいと考える人」の指標に関しては、日本は80%と非常に高い数値になっています。つまり要約すると、「日本では、従業員が在宅での勤務を望んでいるのにも関わらす、企業が認めていない」ということになります。もちろん、テレワークを導入できるかどうかは、業種や業態、仕事の内容などによって異なります。しかしながら、この数値は決して無視できるものではありません。特に、「従業員の安全確保」を考えた時には、非常に深刻な数値と言えるでしょう。
この先の近い未来でも人口減少や異常気象、感染症など、今までに経験したことのない問題に直面するでしょう。そうした時に、一人ひとりがこれまでの仕事のやり方やコミュニケーションの取り方を変えていき、変化に適応しなければならない時代にさしかかっているのです。
コミュニケーションの変化
テレワークの導入は感染症対策のひとつですが、結果的にコミュニケーションの変化をもたらしました。今までオフィスで働いていた人達が異なる場所で作業をすることで物理的な距離が生まれ、それを埋めるようなコミュニケーション手段が活発に使われるようになったのです。例えば、自宅にいても会議に参加できるWeb会議や場所を選ばずテキストでコミュニケーションできるチャットツールがあります。こうしたツールを使うことで、コミュニケーションが阻害されていた問題をある程度解消できており、メリットを感じている方も多いのではないでしょうか。
さらに社内だけでなく、顧客や生活者とのコミュニケーションも変化しています。書店などの小売業では、事前に登録した顧客が自身でロボットを遠隔操作し店内を移動しながら本を探したり、店員にオススメの本を聞いたりなど距離を保つ施策を実施しています。
また不動産業界では、VR(仮想現実システム)の導入が進んでいます。VRによる「内覧」とWeb会議による「重要事項説明」を組み合わせ、鍵の受け渡し以外をすべて非対面で行うサービスも始まりました。リモートワークの導入が進んだものの、自宅がオフィスワークをできる環境ではなく、この機会に新しい住まいを探す方も多いようです。そうした方のためになるべく感染のリスクを減らして新居を探すことができるようになってきました。
このようにコミュニケーション手段を変化させることで、ビジネスプロセスをインターネット上で完結する方向に向かっています。もちろん、工場や接客などインターネットで完結できない仕事も多数あります。そうした仕事の一部分も今後は新しいコミュニケーションをうまく活用して、ゆるやかにデジタル融合していくでしょう。
感染症拡大で注目されている取り組みが、テレワークも含めた「ソーシャル・ディスタンス」です。ソーシャル・ディスタンスとは、「社会距離拡大戦略」のことです。感染症が拡大しているときに、一人ひとりが他者から一定の距離を保つことで、感染拡大を最小限に抑える手段です。新型コロナウイルスも現在は対処療法しかないため、ソーシャル・ディスタンスが最良の手段とされています。これは政府が強制できるものではなく、一人ひとりの心がけによって実現するため、SNSでも「#social distance」のタグをつける呼びかけが増えました。
では、「一定の距離」とは、どのくらいの距離なのでしょうか。
WHO(World Health Organization:世界保健機関)では咳やくしゃみをする人との間に少なくとも1mと定義しています。この距離は国によって定義が違っています。オーストラリアでは1.5m、米国では1.8m、英国は2mという目安があります。日本では正確な定義はありませんが、一般に2mを推奨しています。新型コロナウイルスの感染経路は、せきやくしゃみ、会話で飛び散るしぶきを浴びることで感染する「飛沫感染」とウイルスが付いた手で口や目を触る「接触感染」の2種類があります。飛沫感染の元となるしぶきは水分の重さによって2m以内に落下するというのが、この距離の根拠です。
もちろん電車やバスなどの公共交通機関やコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどでの中で2mという間隔を空けるのは難しいのですが、なるべく人と人との距離を取ることを皆が心がけることで、感染が拡大することを防ぐことができます。
ソーシャル・ディスタンスについて、企業のビジネスプロセスにおいてはどのような工夫がされているのでしょうか。
インターネット関連事業を行うA社では、今回の新型コロナウイルス感染拡大により、多くの企業に先駆けて1月から大規模なリモートワークを導入しました。2011年の東日本大震災以降、有事の際のコミュニケーションラインの確保やリモートワークへの切り替えなどの訓練を行ってきたため、大きな混乱なく導入できたといいます。リモートワーク期間中も、従業員が自ら朝礼や終礼の開催をしたり、Web会議や打ち合わせのルールを決めたりするなど、コミュニケーションが円滑に運ぶような工夫をしました。また、企業側もアンケートを実施して、課題を抽出し、問題の解消に努めています。特筆すべきは、アンケート結果を広く公表していることです。社外に対して社会的距離の取り方についてうまくいった点だけでなく、問題点も公表することで、他企業が参考になるような情報となっています。
また、製造業のB社では、Web会議を使って本社工場から顧客へ提案する活動を始めました。説明員がプレゼンテーションを行うのは対面のプレゼンテーションと同様ですが、Web会議の場合は本社の設計担当者が同席することで、今まで持ち帰っていた専門的な質問にも答えることができます。また、顧客の要望に応じて、マイクやカメラを工場内に持ち込み、生産体制や事業継続計画(BCP)について視察できるようにしました。
企業として社会的な距離をとることを推進すると、取引先に迷惑がかかる、営業活動が阻害されると思いがちですが、この企業の事例は、顧客満足度を高めつつ、社会的な距離を保つことができた好例と言えるでしょう。
海外ではソーシャル・ディスタンスを「フィジカル・ディスタンシング」という言葉で言い換えていることも多くなりました。つまり物理的距離はあっても、寄り添える関係になるという意味合いを込めています。
今回、急に導入されたテレワークで、孤独感を感じている人もいるでしょう。人との接触が少なくなることで不安が募ることもあるかもしれません。しかし、紹介した企業の事例のように、否応なく社会的距離を取るなかで、新しく生まれた価値もあります。例えばWeb会議を導入することによって、電話では難しかった相手の反応がわかる、なかなか話す機会も少なかった遠方の人とコミュニケーションがとれる、あるいはチャットツールを使うことで、今までになかったコミュニケーションが生まれた、といった効果も見え始めています。このように新しい手法や価値などが新常識となるニューノーマルの時代に差し掛かっています。
対面コミュニケーションで得られる価値は大きなものです。しかし物理的な距離があっても、コミュニケーション手段を変えていくことで、新たな価値が生まれる可能性もあるのです。
このニューノーマルに移行しつつある中、企業やブランドがどのように対応していくのか人々は注目しています。今後の予測が非常に困難ですが起きてしまった問題や課題については、創意工夫次第で対処することができると言えます。例えば流通遅延が発生した場合、率直に原因をクライアントや生活者に伝えると同時に、対応策や改善策を平常時と変わらず真摯に示すことで、人々の記憶に刻まれ感染症収束後の高いロイヤルティを勝ち取ることに繋がります。もちろん積極的な社会貢献も同様に高いロイヤルティを勝ち取る要素の一つと言えるでしょう。
世界でも有数な広告会社の一つでもあるCriteo社では、「未曾有の状況下の消費者に関するインサイト」を展開しており、クライアントへの意思決定のサポートに役立てています。
また、有名ブランドの一つであるカナダグース社では、「レスポンス プログラム」と称し二つの工場を解放。従業員の安全を第一に、働く人数やソーシャルディスタンス、衛生面を考え、医療用のスクラブとガウンの生産作業を実施しています。
そして、「マーク ジェイコブス(MARC JACOBS)」と「ヴァレンティノ(VALENTINO)」が、任天堂のゲーム「あつまれ どうぶつの森」の服のデザインの配布を開始したり、ニューヨークメトロポリタン美術館は、同美術館収蔵の作品を取り込めるようにするなど、エンターテインメントの一つでもあるゲーム業界でも異業種とのコラボレーションが盛んに行われています。また同ゲーム内にてテレワークを実施する企業が現れたりしています。
このような異業種とのコラボレーションの取り組みは、「顧客にさらなる価値を提供するためには何が必要なのかを考え抜き実行する顧客中心主義」であるとともに高いロイヤルティを勝ち取る要素の一つとなります。
TEDでビル・ゲイツは、次のアウトブレイク(疫病大流行)のシナリオに沿った計画立案やワクチンの開発、医療従事者のトレーニングなどあらゆる最善の方法やアイデアを実現する時だと2015年に訴えていました。しかしながら当時は人たちには今の状況を予測できなかったのはもちろんのこと、準備もほとんどしなかったのです。
今後も長く続くかもしれない感染症との戦いでは、従業員の安全とビジネスの継続を守るためにデジタル上でのつながりがニューノーマルとなり、早急な移行が国内外で求められています。
さらに、緊急事態宣言が解除された後、企業内にて「social distance」の対策が無い状態で、全ての従業員を出社させる場合は非常に高いリスクを伴うことを企業側は理解しておかなければなりません。既に二桁の感染者数が続き「第2波」の懸念が強まっている事象もあるのです。このようなことから、テレワークやリモートでの業務を継続する、もしくは検討・導入し「新しい働き方」を「新しい日常や常識」にシフトしていく必要があります。
国内においても様々な企業が従業員の出社を再開させていますが、テレワークを継続したり、押印のために出社させるもしくは出社する行動をやめ電子化にしたり、出社させる従業員の上限を5割に抑えるなどの対策を講じ、従業員の安全確保につとめ、ニューノーマルに移行し、医療崩壊をさせないようにしているのです。
例えば、コールセンターで働く人の多くは3密(密閉・密集・密接)環境を強いられていますが、「情報管理が重要だから、密室での勤務はどうしようもない。」といった常識を覆し、コールセンターを全面的に在宅化したチューリッヒ保険日本法人のような取り組みを実施している企業もあります。
これらの新しい常識は中長期的に見れば、紙や印刷代の経費削減や作業工数削減など、企業側のメリットに繋がる可能性があります。
香川県の学校では、地元の養殖として知られるブリを用いたユニークなソーシャルディスタンスの距離をとる指導方法を実施。約2mにあたる「2匹のブリのイラスト」を校内の壁や階段の手すりなどに貼り、距離をとるよう子供たちに呼びかけています。
果たして私たちはソーシャルディスタンスの距離を守れているのでしょうか。
以前のような日常に戻ることは非常に難しいのかもしれません。しかし、私たち一人ひとりが創意工夫し、変化を恐れず、今できることを考え抜き実践していくことで「新しい常識・新しい日常」の「ニューノーマル」になっていくのです。
#社会的距離を保とう
#social distance
#keep distance
#新しい常識
#新しい日常
#new normal
最後に、ナイキのキャンペーンをご紹介します。ナイキは、人々が今パンデミックを乗り越えるために「YOU CAN’T STOP US」のキャンペーンを展開。逆境を克服したアスリートたちの姿が映し出されています。第3弾となる本キャンペーンムービーは、アメリカの女子サッカー代表である、Megan Anna Rapinoe(ミーガン・アンナ・ラピノー)選手のナレーションによるもので、スポーツは「公平な環境とはどのようなものであるかを提示」し、ひいては「良い未来が実現可能であること」を気付かせてくれるような内容となっています。
#You Can’t Stop Us
日本通信ネットワークでは、企業ごとに、企画立案から構築・運用までワンストップで、ICTソリューションサービスを提供しています。
IT担当者様が、ビジネス拡大や生産性向上のための時間に充てられるよう全面的に支援します。
お問い合わせ・ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。