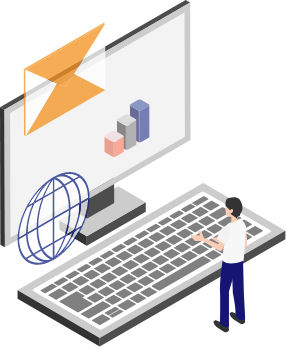新型コロナウイルス感染症の影響で、全世界の「移動」が極端に制限される事態になりました。
今まで対面で行うことが当たり前だった営業活動についても、ソーシャルディスタンスの観点から
オンライン営業やインサイドセールスへの移行が検討されています。
非対面の営業活動は、不確実性高まる「withコロナ」時代において救世主となるのでしょうか。
目次
コロナの影響や労働人口の減少で対面営業が限界に
新型コロナウイルス感染症の拡大は世界中に広がり、いたるところで移動が制限されています。日本も例外ではなく、リモートワークを継続している企業も数多く存在します。そのため今までは訪問回数を増やすことがキーポイントとされてきた営業活動においても対面のコミュニケーションが難しくなっており、大きな影響を与えています。
株式会社エクサウィザーズの調査によると、新型コロナウイルス感染症が与えた影響として、営業活動の遅延を挙げる企業が全体の91%となっており、商品開発の遅延69%と比較しても影響が大きいことがわかります。
長期的な視点においても、労働人口の減少は営業活動においても避けて通れない問題です。経済産業省のレポートによると、労働力となる15歳~64歳までの生産年齢人口が2020年には約60%を占めていますが、その後生産年齢人口比率の減少が加速し、2050年には、50%近くまで減少します。今後は、営業担当者を増やして訪問回数を増やしていく施策は難しくなるでしょう。少ない人数でいかに営業力を向上させるかが今後の課題となります。
非対面で行う営業の問題点
こうした背景からオンライン営業やインサイドセールスを取り入れることが注目を集めています。ベルフェイスの調査によると、オンライン商談を導入している企業は全体の約52%。その中の約半数が新型コロナウイルス感染症対策として導入を始めています。
非対面で行う営業は移動時間がかからないため、時間調整がしやすく遠方の顧客も担当できるというメリットがあります。その結果、営業担当者はより多くの顧客を担当できるようになり、営業効率はアップされるはずです。事実、同調査でオンライン商談の効果について「商談コストの削減」「リードタイムの短縮」「商談数の増加」等の項目別で尋ねたところ、訪問商談と比較して「変わらない(遜色ない)」「上がった」と回答した企業が、すべての項目において70%以上となりました。
一方でデメリットも多く、うまく取り入れられていないという声も聞かれます。
新規顧客開拓の場合は、対面で行ういわゆる飛び込み営業を行う企業も多いのですが、これを非対面で行うと、断られやすいというデメリットがあります。また、モニター越しに話をすると、名前や顔を覚えられにくいという問題もあります。
既存の顧客についても、非対面の営業活動では真意をくみ取り難いというデメリットがあります。また、訪問した際に他部署の人を紹介してもらうといった横展開の形で新規案件を増やしていく方法がとりづらくなります。
オンライン営業導入のポイント
非対面で行う営業活動の弱点をカバーして営業効率を最大化させるには、導入の際にポイントを押さえておく必要があります。
1.目的を明確にする
「見込み客や既存の顧客にどのような価値を与えられるか」「どのように売上を増やしていくか、営業コストを削減するか」といった具体的なビジョンを明確にする必要があります。
2.対面営業とオンライン営業の位置づけを定義する
今までの営業活動のプロセスについて棚卸を行い、オンライン営業をどこに適用するかを検討します。
3.KGI、KPIを設定する
オンライン営業を導入することで、業績にどのように反映するのかKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)を定めます。
4.営業プロセスのストーリーを設計する
リードの獲得からナーチャリング、案件化、本提案、クロージングまでのストーリーを設計します。
5.ツールを選定する
オンライン商談や資料の共有等を行うためのツールを設定します。
6.教育を実施する
オンライン営業の目的を共有し、ツールの使い方や名刺交換の代替としてどのような手段をとるかについて教育を実施します。
新型コロナウイルス感染症が終息するまでのその場しのぎと考えてしまうと、中長期的な生産性の向上が望めません。中長期的なビジョンを持って検討する必要があるでしょう。
オンライン営業の事例
それでは実際にオンライン営業を取り入れた事例を見てみましょう。
第一生命がオンラインで保険販売へ
大手生命保険会社でもオンライン営業へのシフトが始まっています。第一生命保険では、業界で初の取り組みとして営業担当者が一度も顧客と対面せずに契約を結べるプロセスを整備しました。
生命保険の業界では企業や個人宅を訪問し、提案から契約・アフターフォローまでを一貫して対面で行ってきました。しかし近年では共働き世帯の増加や防犯意識の高まりにより、訪問することが難しくなっています。さらに新型コロナウイルス感染症拡大によるソーシャルディスタンスの意識の高まりが後押しした形で、オンライン営業に踏み切ることになりました。
導入の際には、営業担当者4万人にスマートフォンを配布してLINEやビデオ会議を活用することで、顧客に十分な説明ができるプロセスを設計しました。また営業担当者には事前にオンラインの研修プログラムを受講してもらうとともに、説明資料を電子化し、スマートフォンでも見やすいようにレイアウトを整備しています。
NECが取り組む営業のデジタルシフト
マーケティングで先進的な取り組みをしていることで知られるNECにおいても、営業のデジタルシフトは難しいとされてきました。しかし、2005年にインサイドセールスを立ち上げたことがきっかけでデジタル化が進み、今では相手企業の経営層との商談でも95%がオンラインで行われています。
この事例ではマーケティングの中にインサイドセールスの部署を作ったのがポイントです。マーケティングがリードを獲得したのち、インサイドセールスで確度を高め、営業に引き渡すという連携プロセスを作りました。そして営業担当者は顧客に会って課題をヒアリングするのではなく、データを活用することで顧客の潜在的な課題を先取りして提案するという考え方に転換したのです。このように顧客に対面する頻度を少なくしても価値ある提案ができるようにプロセスを常に改善しています。
コロナ禍の営業メゾット「シン・セールス理論」とは
セレブリックス社が提唱する「シン・セールス理論」とは、「セールスのコンテンツが主役の営業スタイル」であり、「この人(企業)から今買いたい」という「購買体験」を抱かせることです。
今までの「購買のノーマル」が、不要不急という世界情勢や風評・自粛などにより、顧客の購買する意思決定にブレーキがかかり、「先ずは(とりあえず)会う」から「必要な時に会う」へ変化しています。
コロナ禍で、「製品やサービスを導入する重要性や緊急性を顧客に気付かせる」ためには、非対面を含めた、タッチポイント毎に提供するコンテンツやコミュニケーションを変えることが必要です。
つまり、「新しい価値」を作ることがテーマとなります。
「新しい価値」を作るためには営業担当部署だけではなく、あらゆる部署にて営業マインドを持ち、MA(Marketing Automation)や、SFA(Sales Force Automation)といったデジタル技術を駆使しながら、全社で取り組む必要があります。
リアルとデジタルを組み合わせて新しい価値を作れるか
先ほどご紹介したベルフェイスの調査では、オンライン商談は対面と比較しても遜色ないあるいはより効果があったという回答が7割を超えていました。
回答結果からみると、オンライン営業やインサイドセールスはリード獲得の救世主になったと言えます。しかし、同調査において「コロナ収束後もオンライン商談を継続したいと思うか」と質問したところ、「続けたくない」と回答した企業が22.9%となっており、対面営業の方が効果があると考える企業が一定数いるということがわかります。このまま元に戻ると、労働力不足という中長期的な課題が解決できなくなってしまいます。
ご紹介した2つの事例では、中長期的な課題を見据えて取り組んでいます。事例からわかるのは、オンライン営業ならではの「新しい価値」を作ることが大切だということです。対面営業と組み合わせていかにシナジーを生み出していくかが、「withコロナ」時代における営業戦略のカギを握ります。
日本通信ネットワークでは、企業ごとに、企画立案から構築・運用までワンストップで、ICTソリューションサービスを提供しています。
IT担当者様が、ビジネス拡大や生産性向上のための時間に充てられるよう全面的に支援します。
お問い合わせ・ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。