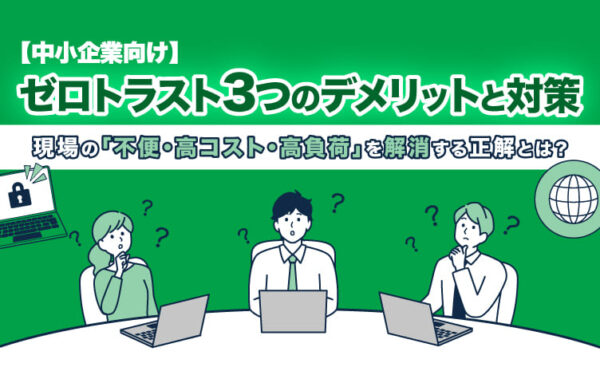
セキュリティ 2026.02.04
2025.11.10
セキュリティ

現代のビジネスシーンにおいてWebサイトの利用は欠かせません。
とはいえ、なかには悪質なサイトも存在するため、むやみにアクセスするのは危険です。
Webフィルタリングは、業務で安全にサイトを活用するための、有効な対策のひとつです。
本記事では、Webフィルタリングでできることや、種類、選定のポイント、注意点などについて解説します。

Webフィルタリングとは、インターネット上の有害サイトや業務に不要なサイトへのアクセスを制御する仕組みです。
アクセス先のURLやドメインをデータベースと照合し、あらかじめ設定したルールに従って許可・遮断を行うといった流れでアクセスを制限します。
主にURLやカテゴリ、キーワードを基準にしてアクセスを制限するため、情報漏洩、業務効率の低下を防ぐうえで有効なセキュリティ対策です。
企業や教育機関での利用が一般的で、セキュリティリスクが高まっている現代において、安全で生産的なネット環境を維持するために欠かせないものになっています。

Webフィルタリングを導入すれば、危険なサイトへのアクセスを制限し、セキュリティリスクを抑えることが可能です。
また、従業員が業務に集中できる環境を構築できるため、組織の運営を支える役割も果たします。
Webフィルタリングを用いて危険性の高いWebサイトへのアクセスを制御すれば、情報漏洩やマルウェア感染といった外部リスクを防ぐ効果が期待できます。
例えば、従業員が誤って悪意のあるサイトやコンテンツにアクセスした場合でも、ウイルスが侵入する前にブロックできるので、被害の拡大を最小限に抑えられます。
また、SNSやクラウドストレージなどへの不用意なアクセスを制限すれば、不正なデータ流出も未然に防げるでしょう。
Webフィルタリングの活用により、顧客データや機密情報を含む社内ネットワーク全体の安全性を高められます。
参考記事:情報漏洩による損害賠償の相場は?事例から読み解く金額やリスク
Webフィルタリングは、セキュリティ対策だけでなく、組織全体の生産性向上や内部統制の強化にも寄与します。
例えば、業務に関係のないサイトへのアクセスを制御することで、従業員が不要なWeb閲覧に時間を割くことを防げます。
その結果、従業員が作業に集中できる環境が整えば、生産性の低下を回避し、効率的な働き方が実現できるでしょう。
また、Webフィルタリングには、アクセス履歴をログとして記録する機能が備わっているため、従業員がどのサイトを利用しているかを可視化できるのも利点です。
これにより、不適切な利用や内部不正を早期に把握できるほか、証跡管理、コンプライアンス遵守の観点でも有効に機能します。

Webフィルタリングには、以下の4種類があります。
それぞれ特徴とメリットが異なるので、適切な方法を選べるよう、違いを把握しておきましょう。
ブラックリスト方式は、あらかじめ危険性が高いと判断されたサイトや業務に不要なサイトをリスト化し、それらへのアクセスを遮断する仕組みです。
既知の不正サイトや有害コンテンツを効率的にブロックできるため、利便性と安全性のバランスがとりやすい点が特徴です。
ただし、新たに登場する悪意あるサイトには対応が遅れる可能性があるため、適宜、速やかなデータベースの更新が必要になります。
ホワイトリスト方式は、あらかじめ管理者が許可したサイトだけにアクセスできる仕組みです。
リストに含まれないサイトへのアクセスはすべて遮断されるため、信頼できるサイトのみを利用でき、高いセキュリティを実現できます。
一方で、業務で利用するサイトが増えるたびに登録作業が発生するため、運用面での柔軟性に欠ける点には注意が必要です。
カテゴリフィルタリング方式では、Webサイトを「業務」「ニュース」「SNS」「アダルト」などのカテゴリに分類し、不要なカテゴリだけをまとめて制御します。
管理者が業務に不要なカテゴリを一括で遮断できるため、運用効率が高いのが特徴です。
ただし、サイトの分類精度に依存するため、誤って必要なサイトが制限される可能性もあります。
そのため、「マーケティング部門ではSNSにアクセス可能」といった、セクションごとの柔軟な設定が求められます。
レイティング方式は、Webサイトに付与された「安全性や内容に関する評価点(レイティング)」を基準にアクセスを制御する方法です。
評価の方法には、管理者自身が設定するものと、第三者機関によって評価されるものの2種類があります。
あらかじめ設定した基準値を上回るサイトのみを許可できるため、柔軟かつ段階的なフィルタリングが可能です。
一方で、評価データの正確性や更新頻度に左右されるため、信頼性の高いレイティング情報を利用することが重要です。
また、高い効果が得られる反面、評価基準の設定や更新管理など、運用の手間が増える点には注意が必要です。

Webフィルタリングを選ぶ際は、セキュリティの強化が図れることはもちろん、以下のような要素を比較検討する必要があります。
実際の運用状況を考え、適切なサービスを選びましょう。
Webフィルタリングでは、アクセス制御の判断をデータベースに基づいて行うため、その精度の高さがセキュリティ効果を左右します。
とくにカテゴリフィルタリング形式の場合、精度が低ければ誤って業務に必要なサイトが制限されてしまう可能性があるため、十分に確認しなければなりません。
データベースの精度が高ければ、危険なサイトを確実にブロックしつつ、重要なサイトへのアクセスを誤って制限するリスクを減らせます。
導入時には、利用の快適さとセキュリティリスクへの効果を考え、更新頻度、網羅性に優れた信頼性の高いデータベースを選ぶことが重要です。
Webフィルタリングを導入する際は、自社の業務内容や利用環境に応じて、柔軟にアクセス制限を設定できるかどうかが重要です。
例えば、部署や役職ごとに閲覧可能なサイトを分けられるような細かなポリシー設定が可能であれば、運用担当者の管理負担を軽減できます。
一方、設定の自由度が低いと、必要なサイトまで閲覧できなくなるなど、業務効率の低下につながるおそれがあります。
さらに、操作画面が複雑だと正しい設定を行いにくくなるため、管理画面の使いやすさもあわせて確認しておくとよいでしょう。
Webフィルタリング製品には、社員のアクセス状況を可視化できるレポート機能や、設定を一元的に操作できる管理機能が備わっていると便利です。
レポート機能があれば、従業員がアクセスしているサイト、利用している時間帯などを管理者が明確に把握できます。
これにより、不審なアクセスや業務外利用を早期に発見し、適切な対応につなげることが可能です。
管理機能が充実している製品を選べば、セキュリティ強化と運用効率化を同時に実現できます。
Webフィルタリングを導入する際は、提供される機能とコストのバランスを見極めることが重要です。
いくら高機能であっても、自社の規模や利用目的に合わなければ、コストが過剰になる可能性があります。
必要なセキュリティレベルや運用体制に応じて費用対効果の高い製品を選べるよう、トライアルなどを活用して複数のサービスを比較してみましょう。
Webフィルタリングを導入する際にはそれによって業務に支障が出ないよう考慮する必要があります。
また、使う側の意識によっては十分なセキュリティ効果が得られないため、従業員のITリテラシーを高めることも重要です。
セキュリティ対策としてフィルタリングは重要ですが、よく使うサイトにも制限をかけてしまうと、アクセスに時間がかかってしまいます。
そうなれば業務効率が低下しかねないため、あらかじめ利用サイトを洗い出し、導入前にフィルタリングを行う範囲を決めておく必要があります。
また、悪質でないにも関わらず、フィルタリングの仕組み上制限がかかるようなサイトへの対応として、例外的な運用ルールを設定することも大切です。
Webフィルタリングを導入したからといって、セキュリティリスクを100%回避できる訳ではありません。
例えば、危険なサイトがブロックされても、添付ファイルやフィッシングメールから被害に遭う可能性は残ります。
導入にあたっては、その機能を過信せず、利用者のITリテラシーを高めることも重要なポイントです。
Webフィルタリングの限界、有害サイトの見分け方、情報セキュリティ事故の事例・予防策などを利用者が学ぶことで、より被害を防ぎやすくなります。
業務効率を高めるために、Webサイトの利用は欠かせませんが、中には悪質なサイトも存在するため注意が必要です。
Webフィルタリングを導入すると、情報漏洩やウイルス感染などのセキュリティリスクを軽減することが可能です。
また、従業員のインターネットへのアクセス状況が把握できるので、不適切な利用や生産性の低下を防ぐのにも役立ちます。
フィルタリングの方法や機能はいくつかあるので、自社のニーズに沿った適切な方法を選択しましょう。

「FLESPEEQ UTM」は、ウイルスやハッキング等のあらゆるサイバー脅威から、ネットワークを多層的に守るセキュリティ機器です。
フィルタリング機能に加え、IDS(不正侵入検知システム)やIPS(不正侵入防御システム)といった複数のセキュリティ機能が備わっているのが特徴です。
また、フィルタリングの設定追加対応など、運用サポートもご提供しているので、専任のIT担当者がいない場合でも安心して導入できます。
セキュリティ強化の必要性を感じている企業様は、ぜひ詳細をご覧ください。
日本通信ネットワークは、企業ごとに、企画立案から構築・運用までワンストップで、ICTソリューションサービスを提供しています。
IT担当者様が、ビジネス拡大や生産性向上のための時間を確保できるよう、全面的に支援します。
お問い合わせ・ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
サービスに関するご質問、お見積りご相談他、
お気軽にお問い合わせください。
※弊社休日のお問い合わせにつきましては
翌営業日以降の回答となります。 ご容赦ください。