
セキュリティ 2025.12.01
2025.09.08
セキュリティ
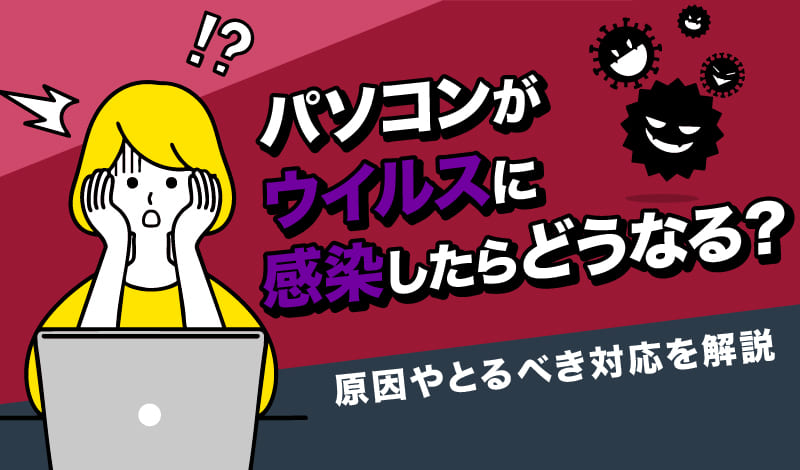
現代のビジネスシーンに欠かせないパソコンは、常にウイルス感染という見えないリスクにさらされています。
企業のパソコンがウイルスに感染すると、データの損失や顧客情報の漏洩、業務停止などに発展し、顧客や取引先からの信頼を失うおそれがあります。
そのため、平時からウイルス対策を徹底したうえで、万が一感染した際には早期の対応が重要です。
この記事では、パソコンがウイルス感染する原因や、感染時の症状、感染を未然に防ぐ方法などについて解説しています。ぜひ参考にしてください。

パソコンがウイルスに感染する主な原因としては、以下が挙げられます。
一見無害に見えるケースも多いことから、リスクを冒した自覚がないまま、被害に遭ってしまうケースが後を絶ちません。
各原因について、詳しく見ていきましょう。
メールに添付されたファイルを開くことでウイルスに感染したケースは、数多く報告されています。
ウイルスに感染する可能性があるファイルは以下の通りです。
また、本文中に貼られたURLから不正サイトに誘導され、ウイルスが自動的にダウンロードされるケースもあります。
近年では、既存の取引メールや決済メールに偽装するケースも見られ、以前より見分けにくくなっているため注意が必要です。
メールを見ただけで感染する仕組みもあるため、開く前に、メールアドレスなど情報を念入りに確認しましょう。
不正なWebサイトへアクセスすることでウイルスに感染するケースもあります。
次のような感染経路が該当します。
メール同様、URLや文章の不自然さなどからサイトの信頼性を確認することが重要です。
ウイルスが仕込まれた外部記録媒体をパソコンに接続してしまうと、ウイルス感染するリスクが高まります。
外部記録媒体には、以下のようなものがあります。
例えば、USBに自己増殖型のウイルスが仕掛けられている場合、接続したパソコンを介して他のUSBにも感染が拡大する可能性が高いでしょう。
他人から借りたUSBや、会社・学校など複数の環境で使い回された記録媒体はとくに危険です。
外部記録体を使用する際は、事前にウイルススキャンを実行するほか、USBなどに対してもセキュリティ対策を施すことが求められます。
パソコンがウイルスに感染すると、さまざまな症状が現れます。
代表的なものは以下のとおりです。
こうした症状を正しく理解しておくことで、万が一、感染してしまった場合でも早期に対応でき、被害の拡大を防ぐことが可能です。
パソコンがウイルスに感染すると、画面に次のような警告メッセージや広告が表示されることがあります。
これらは、ウイルスの制作者が表示させている偽の警告です。
ユーザーを不安にさせて不正なソフトをインストールさせたり、金銭を騙し取る詐欺ページへ誘導したりするための手口です。
実在の企業名を名乗って偽の警告文を流し、偽サイトへ誘導するケースもあるため注意しましょう。
パソコンやアプリの動作が遅くなったり、頻繁にフリーズしたりする場合は、ウイルス感染が疑われます。
ウイルスの動作によって、CPUやメモリが大量に消費されると、突然シャットダウンしたり、パソコンが起動しなくなったりする可能性もあります。
その結果、作業が中断されたり、入力中のデータが消えたりすれば、業務効率や信頼性に影響を与えかねません。
また、以下のような原因で不具合が発生することもあるので、広く原因を探ることも大切です。
フリーズや動作遅延などが起こったときは、ウイルス感染以外の原因がないかもチェックしてみましょう。
ウイルスに感染すると、ユーザーの操作とは無関係に、ファイルやデータが削除されたり、作成した覚えのないデータが勝手に増えたりすることがあります。
知らないアイコンがデスクトップに追加されている、以前あったアイコンがなくなっているといった事象が起きるケースも少なくありません。
また、ウイルス感染により、知らないうちにメールを送信しているなどの異常も生じがちです。
第三者がこのメールを開けば、ウイルス付きのファイルや偽サイトへの誘導で、相手が被害を受けるかもしれません。
このほか、アカウントが乗っ取られれば、パスワードを変更される、メールの管理画面にアクセスできないなどの被害につながります。
不審な送信履歴を見つけた場合は、即座にパスワードを変え、ウイルススキャンを実施するのがおすすめです。
ウイルス感染すると、インターネット接続に以下のような不具合が見られることがあります。
これは、ウイルスが大量の通信を行ってCPUのリソースを消費したり、遠隔操作されたりするのが主な原因です。
ルータやモデムに不調がなく、適切にメンテナンスを実施しているにもかかわらず通信に異常が見られる場合は、ウイルス感染を疑ってみましょう。
パソコンがウイルスに感染してしまった場合、冷静に以下のような対応を取り、被害の拡大を防ぎましょう。
感染したまま放置していると、個人情報の漏えいや金銭的被害、さらには他の機器、ネットワークへの二次感染へとつながりかねません。
ウイルスに感染した場合はすぐにネットワークから切断し、感染の拡大や情報漏洩を防ぐことが重要です。
ウイルスはネットワークを通じて外部のサーバーと通信し、個人情報を送信したり、さらなるウイルスをダウンロードしたりする恐れがあります。
接続方法ごとに、次の方法で切断しましょう。
パソコンからオフラインにする方法は、使用するOSや機種によって異なるので、取扱説明書、OSのサポートサイトなどで確認してください。
パソコンをインターネットから切り離したら、セキュリティソフトを起動してウイルススキャンを実行しましょう。
ウイルスが検出された場合は、スキャン結果に応じてウイルスの削除や隔離などを行ってください。
適切に作業を行ったら、ソフトを再び起動してスキャンを実行し、ウイルスが完全に駆除できたことを確認します。
なお、無料のセキュリティソフトでは対応できない高度なウイルスも存在するため、できれば信頼性の高い有料ソフトを利用するのがおすすめです。
万が一ウイルスの削除ができなかった場合は、後述する「削除できなかった場合の対処法」を参考に、初期化や専門業者への相談を検討しましょう。
ウイルスの駆除に成功したら、情報が漏洩している可能性を考慮して、すべてのパスワードを変更します。
仮に情報漏洩が疑われない場合でも、次のように金銭的被害につながりやすいサービスのパスワードは変更しておくと安心です。
また、パスワードの変更をする際は、スマホやタブレット端末など、感染したパソコン以外のデバイスを使うのがおすすめです。
ウイルス感染したパソコンは、安全が確認されたうえで再起動してインターネットに接続してください。
ウイルスの脅威に備え、強力なパスワードの設定や二段階認証やUTMの導入など、強固なセキュリティ対策の追加もあわせて検討しましょう。
前述のとおり、ウイルスの種類によってはセキュリティソフトを用いても駆除できないこともあります。
その場合、パソコンを初期化(リカバリー)する方法が有効です。
しかし、初期化を実行すると、パソコン内のデータやインストールしたソフト、画像、動画などがすべて消去されます。
いざというときに困らないよう、普段からこまめにバックアップをとるなどして備えておきましょう。
初期化の手順は次のとおりです。
初期化や復元が難しい、感染が深刻で自社での対応が困難という場合は、専門業者のサポートを検討してください。

パソコンにウイルスが感染してしまうと、個人情報の流出や業務データの消失、金銭的な被害などに発展することがあります。
こうした被害を防ぐためには、感染してから対処するのではなく、そもそも感染させないための予防策が重要です。
ここでは、ウイルス感染を防ぐ具体的な方法を紹介します。
ウイルス感染を防ぐために最も有効な手段は、信頼できるメーカーのウイルス対策ソフトを導入することです。
最新のマルウェアや未知のウイルスにも対応できる高性能なセキュリティソフトを選べば、今後より巧妙な手口が登場しても、パソコンを守れる可能性が高まります。
ただし、ソフトを導入して終わりではなく、定期的にウイルススキャンを実施したり、更新切れに注意したりすることが大切です。
また、サービスごとに、性能や価格、サポート内容が異なるため、自社の規模、業務内容、ニーズなどに合わせて選定しましょう。
無料のセキュリティソフトでも一定の保護は可能ですが、企業で大切な情報を扱う場合は、有料で高機能のソフトを選択するのがおすすめです。
パソコンのOSやアプリケーションソフトには、常にセキュリティの脆弱性が存在します。
開発元は、これらの脆弱性を修正するため、定期的に修正プログラムを提供しています。
しかし、修正プログラムを反映するためにはアップデートが必要であり、それを怠ると簡単にウイルスに侵入されてしまいます。
OSや各種ソフトウェアのアップデートがあった場合にはすぐに実行し、常に最新バージョンに保ちましょう。
また、古いOS(Windows7やWindows8など)は、新たな脅威に対処できない可能性があるため、使用しないのが最善です。
見覚えのない送信者からのメールは、基本的に開かないようにしましょう。
また、本文中の不審なリンク、怪しいと思われるサイトにもアクセスしてはいけません。
もし、メールに不審な添付ファイルやリンクが見られた場合には、送信先に連絡して確認をとりましょう。
このとき、チャットや電話など、メール以外の手段で確認するのがおすすめです。
このほか、被害事例や最新の詐欺手口などを社内で共有し、信頼できるサイトやメール以外には注意を払うなど、ウイルス感染に関する教育を徹底することも大切です。
パソコンやデータを守るためには、安全性の高い無線LAN(Wi-Fi)の使用を心がけることも重要です。
暗号化方式が古かったり、パスワードが設定されていなかったりすると、脆弱性をついてウイルスを送り込まれかねません。
総務省の「無線LAN(Wi-Fi)のセキュリティに関するガイドライン」では、セキュリティ方式 は「WPA2またはWPA3」の使用を推奨しています。
参考:無線LAN(Wi-Fi)のセキュリティに関するガイドライン|総務省
また、Wi-Fiのパスワードは複雑なものを設定し、定期的に変更するようにしましょう。
公共のWi-Fiやパスワードが設定されていないネットワークを利用しないのも有効なセキュリティ対策です。
このほか、ルータのファームウェアも定期的に更新し、常に最新の状態を維持する必要があります。
万が一のウイルス感染に備えて、重要なデータやファイルはこまめにバックアップしておきましょう。
とくに、ランサムウェアのようにデータを暗号化して金銭を要求するウイルスに対しては、バックアップの存在が対抗手段になるケースもあります。
また、バックアップをパソコン内に保管するのはリスクが高いため、外付けHDDやクラウドストレージ、USBなどへの保存が推奨されます。
ウイルス感染する可能性がある端末とは別の環境でデータやファイルを保管することで、いざというときも重要なデータの復旧が可能です。
バックアップには、3つのデータを複数の媒体で保管し、うち1つはオフラインで管理する「3-2-1ルール」という考えがあります。

画像出典:重要インフラにおける サイバー事案対応
| 項目 | 内容 |
| 3つのデータ | パソコン本体など、3つのバックアップを用意する |
| 2つの異なる媒体 | 複数の異なる記録媒体にデータを保存する |
| 1つはオフラインで保管 | 物理的な別の場所(外部記録媒体など)に少なくとも1つデータを入れる |
こうした適切な保管により、メディアの破損や紛失、ウイルスの脅威などから大切なデータを守ります。
巧妙化するサイバー攻撃に備えるため、ネットワーク全体をさまざまな脅威から保護できるUTMの導入も検討しましょう。
UTMは、ウイルス対策のみならず、スパムフィルタや不正侵入検知・防御など複数のセキュリティ機能を一括で管理・運用できるシステムです。
ネットワーク全体を多角的に守ることで、一つの対策が突破されても別のセキュリティ機能で対処し、被害を最小限に抑えられる仕組みになっています。
たとえば、日本通信ネットワーク株式会社の「FLESPEEQ UTM」のように、導⼊から保守管理までトータルサポートを提供するサービスなら、情報の管理やウイルス感染時の対処といった負担が軽減できる点もメリットです。
パソコンやネットワークのウイルス感染は、業務停止、顧客情報の漏洩などにより、企業の信用を失うリスクがあります。
こうした事態を防ぐためには、OSやセキュリティソフトの定期的なアップデート、データのバックアップ、信頼性の高いウイルス対策ソフトの利用といった対策が不可欠です。
万が一、ウイルスに感染した場合にも備え、日頃から感染経路、感染時の対処法などを確認しておきましょう。
近年、サイバー攻撃の手口が巧妙化し、ウイルスの種類も増えているため、アンチウイルスソフトなど、一つのセキュリティ対策では十分に保護することは困難です。
こうした状況で組織のネットワークを守るためには、複数のセキュリティ機能を備えたUTMの導入が有効になります。

FLESPEEQ UTMは、ウイルス対策やメールフィルタリング、webサイトの閲覧制限など、複数の対策を一つにまとめたセキュリティサービスです。
機能の集約により、高いセキュリティ対策を行いながら、コストの低減も実現しています。
導入時だけでなく、ご要望に合わせて保守サポートにも対応するため、情シス担当者のいない企業様でも安心してご利用いただけます。
オンライン無料相談のほか、メール、電話でのお問い合わせが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
日本通信ネットワークは、企業ごとに、企画立案から構築・運用までワンストップで、ICTソリューションサービスを提供しています。
IT担当者様が、ビジネス拡大や生産性向上のための時間を確保できるよう、全面的に支援します。
お問い合わせ・ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
サービスに関するご質問、お見積りご相談他、
お気軽にお問い合わせください。
※弊社休日のお問い合わせにつきましては
翌営業日以降の回答となります。 ご容赦ください。